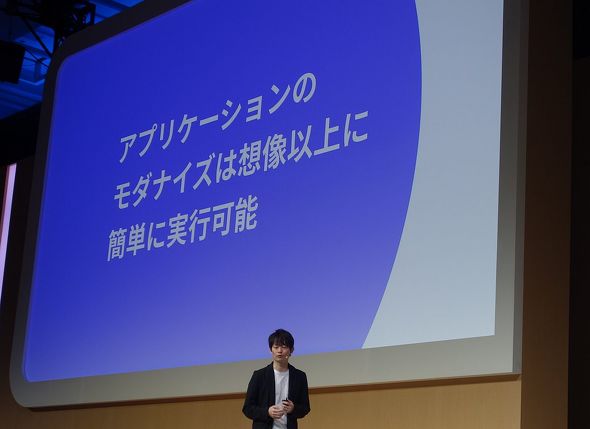Google CloudはAnthosで「次のVMware」になろうとしている FFGはCloud Spannerで次世代銀行システムを開発:Google Cloud Next Tokyo ’19(2/2 ページ)
2019年4月にGoogle Cloudがサンフランシスコで開催した「Google Cloud Next ’19」で正式提供開始を発表したAnthosは、マルチクラウドコンテナ基盤ソリューション。Googleがリードしてきたコンテナオーケストレーションのオープンソースソフトウェア(OSS)であるKubernetesを中核に、サービスメッシュのIstio、サーバレスのKnativeなどの技術要素で構成され、管理ユーザーインタフェースを備えている。
ユーザー組織がAnthosを、オンプレミスのITインフラ(VMware vSphere)上に導入すると、その後はセキュリティアップデート、バージョンアップなど、コンテナ基盤の基本的運用をGoogle Cloudが担う。オンプレミスのコンテナ基盤はGKE上の自社コンテナ環境と統合管理できる。また、AnthosはAmazon Web Services(AWS)やMicrosoft Azureにも導入可能としており、「OSSでマルチクラウドを実現できる」と同社は強調する。
AnthosにおけるGoogle Cloudの狙いを最も分かりやすく表現すると、「次の時代のVMwareになろうとしている」ということになる。VMwareは、サーバ仮想化によってさまざまなサーバハードウェアを抽象化するプラットフォームを構築し、サーバ統合や運用自動化などの価値を提供してきた。だが現在、多くの企業が進めようとしているのはハイブリッド/マルチクラウドの活用であり、異種クラウドの抽象化が、次のテーマになってくる。
すると、仮想マシンレベルでの思考には限界もある。クラウド間でハイパーバイザーを統一できるわけもなく、単一の仮想マシンを、何の手も加えずに、あらゆるパブリッククラウドで動かすという世界は実現できそうにないからだ(これを、ある意味で逆手に取り、パブリッククラウドの施設内でVMwareのクラウド基盤を動かすのが、「VMware Cloud on AWS」などのサービス)。
そこで抽象度を上げ、異なるクラウドをコンテナレベルで抽象化するプラットフォームを提供するというのが、Anthosの狙いだ。オンプレミスやGCP以外のパブリッククラウドでAnthosを使ってくれれば、まず多くの企業が関心を寄せるコンテナ基盤を即座に導入でき、次にGCP上のGKEと合わせ、マルチクラウドの統合環境が構築できるということになる。これは、「Anthosを使えば、アプリケーションレベルのマルチクラウド管理ツールが手に入りますよ」というメッセージでもある。
そしてこのアプリケーションレベルのマルチクラウド管理ツールは、Google Cloudが(コンテナ基盤自体の)運用を担う。また、サーバレスを実現するKnativeを含んでいるため、ユーザー組織はインフラ管理から解放され、アプリケーションに専念できると、同社はアピールする。料金は、Anthosを稼働する拠点の数やコンテナの稼働比率に依存せず、総体としてのコンテナ稼働規模に基づく。このため、Anthosのコストという観点で、ユーザー組織はアプリケーションをどこでどのくらい動かすかは考えなくていい。これをヘルツル氏は、「あなたのペースでクラウドを活用できる」と表現する。しかも、Anthosは全ての要素がOSSであるため、ロックインがないとする。Anthosを使いたくなくなった際には、主要パブリッククラウドの全てが提供しているKubernetesコンテナオーケストレーションサービスに移行する選択肢もある。
Google Cloudの狙いを探る意味で非常に興味深いのは、上記の料金体系だ。ユーザー組織がAnthosをオンプレミス中心で使おうが、GCP中心で使おうが、同サービスを使ってくれる限り、Google Cloud側の売り上げは変わらない。すなわち、Google CloudはAnthosに関しては、GCPに顧客を誘導する必要がない。
ある顧客がAnthosを100%オンプレミスで使うとしても、Google CloudにとってはGCPを使ってくれるのと同じ売り上げになる。GCPで100%使ってくれた方がありがたいことは確かだが、そうでなくてもAnthosを使ってくれる限り文句はないということだろう(また、100%オンプレミスでAnthosが使われた場合でも、GCP上の機械学習/AI系サービスを活用してもらうことが可能だ)。
つまりGoogle CloudはAnthosで、クラウドベンダーというよりも、ソフトウェアベンダーとして振る舞っている。 これが「次のVMware」の意味だ。サーバ仮想化の次がKubernetesによるコンテナ環境であるなら、Google Cloudは次のVMwareになろうとしている。Red Hatと同じように、エンタープライズにおけるコンテナインフラの主要ベンダーになろうとしているのだ(一方VMwareもサーバ仮想化からコンテナに、いつかエンタープライズの注目が移行する可能性を察知しているからこそ、Kubernetesプロジェクトを始めた3人のうち2人が創始した企業、Heptioを買収した)。
とはいえコンテナは、一般的な企業のIT運用チームにとって新しい世界であり、飛びつくきっかけを見出しにくい。そこでGoogle CloudはAnthosを、ヘルツル氏の言葉通り「気軽に実行できるアプリケーションのモダナイゼーション手法」として推進している。
「既存のシステムをどうするか」は、世界中の企業にとって大きな課題だ。かつてVMwareは、既存システムを仮想化し、同社のプラットフォーム上に移行することで、延命ができるとアピールした。現在のGoogle Cloudが打ち出しているメッセージも、これと全く同じだ。
Google Cloudは今回のイベントで、仮想マシンをコンテナに自動移行するツールである「Migrate for Anthos」で、β版の提供を開始したと発表した。オンプレミスのvSphere上で動く仮想マシンに加え、AWSやAzureの仮想マシンのコンテナへの変換にも対応したという。
Anthosと「Google Cloud VMware Solution by CloudSimple」の関係
Google Cloudは、一般企業における既存システムのコンテナへの移行が一挙に進むと考えるほどナイーブではない。企業が抱える「既存のシステムをどうするか」という課題に向けた選択肢の一つとして、同社はVMware Cloud on GCPとも表現できる「Google Cloud VMware Solution by CloudSimple」を、今回のイベントの前日に米国で発表した。
これについて、前出のヘルツル氏に直接、「Anthosとの対比で、『Google Cloud VMware Solution by CloudSimple』をどう表現するか」と質問してみた。答えは次の通りだ。
「完全に顧客の選択次第だ。ワークロードをvSphereで運用することに安心を感じており、これを自社データセンターの外でやりたいなら、GCPでもできるようになる。AWSやAzureのVMwareサービスと同様だ。vSphereをGCPの隣で動かせるため、クラウド上のサービスとの連携がやりやすい」
ヘルツル氏は、現実的にいって、Windowsサーバ上のアプリケーションはAnthosに移行しにくいため、当面はそのままにしておく判断をするケースもあると話した。
「あなたの組織がvSphereに満足しているなら、私たちはクラウドとしてこれをサポートする必要がある」
「一方Anthosは、『あなたたちはインフラ運用から完全に解放されるべきだ』というメッセージに基づく。Anthosは(オンプレミスでは)vSphere上で動くが、サービスの構成はvSphereではなく、Anthosによって行われる。例えばファイアウォールの設定は運用担当者自身ではなく、Anthosが行う。ただし、VMwareの機能を完全に排除しようというのではない。VMware NSXと連携し、Anthosのコンテナワークロードに対して、マイクロセグメンテーションを自動的に適用できる。vSphereがインフラそのものであるのに対し、Anthosはアプリケーションやサービスといった、より高いレベルの環境だ」
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.