第298回 Armが方針転換? 「設計図だけでなく自前の半導体製品を販売するかも」報道の真相:頭脳放談
英国の経済紙「The Financial Times」が、「Armが自ら半導体製品の販売を検討しており、2025年内にMetaに納品する予定である」と報じた。これまで30年にわたって、半導体の設計(IP)を販売してきたArmが、ライセンス先と競合する可能性のある半導体製品を売るとなると大きな方針転換となる。その背景について考えてみた。
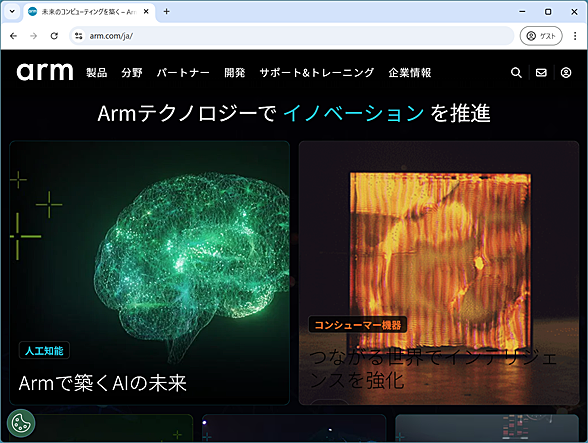
「Armが半導体製品の販売を開始する」可能性について考えてみた
英国の経済紙「The Financial Times」が、「Armが自ら半導体製品の販売を検討しており、既に2025年内にMetaへの納品予定である」と報じた。Armは、半導体関連会社に半導体IP(知的財産権)を販売して成功した会社だ。自ら顧客のライバルとなる道を選ぶのか、また本当に製品を販売できるのか、について考察してみた(画面はArmのWebページ)。
今回はArmについて書かせていただく。ただしArmが公式に発表した話ではなく、英国の経済紙「The Financial Times(FT)」が「その筋」から情報を得て書いた記事が元になっている(FTもArmも英国企業なので、情報の確度は高いかもしれない)。Armのビジネスモデルの変更につながるような話だ。
Armは半導体IPを販売してきた会社だが……
Armといえば、掛け値なくほぼ世界中全ての半導体関連企業にArmプロセッサを中心とする半導体IP(知的財産権)を販売してきた半導体IP業界の巨人である。ソフトバンク系の投資ファンドが主要株主であり、Armの業績はソフトバンクの株価にも影響する。
Arm自体は半導体IP企業として、設計すれども製造販売はせず、というスタンスで30年以上ビジネスを続けてきている。1990年代の欧州携帯電話の勃興とともに成長し、ほぼ全てのスマートフォンにArmが設計したプロセッサが搭載されるようになって、今日に至っている。
そのArmが半導体IPにとどまらず、2025年、自ら半導体製品の販売に踏み出すだろうという記事だ。これが真実であれば、世界中の半導体関連企業がArmのIPライセンスを買ってビジネスしてきているだけに、結構インパクトが大きい方針転換である。いまのところArmもソフトバンクもFTの報道について公式のコメントなど一切出していないようだ。
しかし、FTの報道を受けて、早速株価なども動いたようだ。まだ、どんなものをいつ売るのかなど、本当のところは何も分かっていないのだが……。
ここで記事に真実味を与えているのが、その1番目の顧客としてMetaの名前が挙がっていることだ。どうもMetaが現在注力しているAI(人工知能)向けのプラットフォームに使われるプロセッサになるのではないか、ということらしい。
Armはプロセッサを開発、販売できるのか?
まずは、Armが実際に製品を作れるのか、という点を考えてみよう。現行のArmコア搭載製品の場合、Armはコアとなる半導体IPを各半導体会社に与える。その製造と販売は各半導体会社の責任である。
しかし、この実際の製品(プロセッサ)にする過程については、全く問題ないだろうと想像している。長年にわたってArmは、半導体IPの開発時に評価用のチップを多くのファウンドリの異なるプロセス上で製造してもらい、試験、評価するということを繰り返してきているからだ。製品レベルの設計と試作評価まではお手のもののはずだ。
それどころか、設計リソースの少ない半導体メーカー向けには、入れ込んだ設計の手伝いをした経験もあると思われる。これなど実質的に製品設計を請け負っていることに近いだろう。
そして、製造はTSMCを代表とするファンドリメーカーに委託することになるから、試作してGoを出せば、量産製品を作り出すことはそれほど難しいことではないだろう。
やろうと思えばできるのに、Armが自社での製品販売を行ってこなかったのは、彼らが製品販売のリスクをよく分かっていたからだと思う。Intelのように自社工場にこだわっていると、ひとたび、うまく回らなくなると巨大なリスク(毎月の巨大赤字)となって会社存亡の危機となる。
いまやほとんどの会社が特殊用途の半導体を除き、製造はファウンドリに委託してこのリスクをオフロードしている。当然、製造から手掛ければ、懐に入ったはずの利益の一部は、ファウンドリに行くけれども仕方がない。
続いて製品そのものを売りさばくときのリスクもある。半導体ビジネスは典型的なB2Bビジネスである。一般消費者が現金を持って半導体会社に買いに来ることはない(秋葉原などで売られているのは、半導体商社経由の小売りである)。特に小口で息の長い顧客が多い組み込み用途を考えると分かるのだが、単価が安く、当然ながら利幅も小さい製品がダラダラと長期間売れ続けてしまうのだ。
そして、売りが立ってから実際にお金になるまでの期間も長い。その期間の資金負担、販売管理の手間など考えると、とても面倒なビジネスである。その上、末端市場の動向次第ではせっかく仕込んだ製品が不良在庫になってしまうようなこともあり得る。ひとたび、そういうことが起こるとチビチビ積み上げてきた利益が一瞬で吹き飛んでしまう。
自社製品ではそういうリスクを負わねばならないのだ。その点、IPビジネスは手離れがよい。契約して文書一本で、まとまったお金が振り込まれる。以降、ライセンシーの出荷数量次第でロイヤルティーも振り込まれてくる。特に追加の負担費用がない。IPについてのサポートが必要になることもあるが、サポート料も有償だ。取りっぱぐれなどないのである。
ではなぜいま、Armは製品の製造に乗り出すのか?
そういうリスクを抑えた半導体IPビジネスで長年やってきたArmなのだが、自社製品の販売に魅力を感じるとしたら、どこにあるのか? それはNVIDIAを考えるとよく分かる。
NVIDIAはファウンドリに支払う製造委託のお金の何倍だか何十倍だか分からないが、膨大な利益を製品から生み出せている。自社製品に圧倒的な強みがあれば、自在に製品の値段が決められるのだ。それもあって魅力的な株価を実現している。
一方、Armの場合、(半導体IPとしては)ほとんど世界制覇に近い市場占有率を誇りながらも、そんなボロもうけはできていないと思われる。ライセンス料は契約時に決まっている。適用条件によって金額は変わるとはいえ、多数の会社に複数ケースで提供している以上、一定の相場がある。ロイヤルティーについても同様だ。法外な料率を吹っ掛けることは勝手だが、そういうことはできそうにない。ロイヤルティーなどが不要なRISC-Vが徐々に勢力を増しているからだ(RISC-Vについては、頭脳放談「第256回 AppleもRISC-Vのプログラマーを募集 ところでRISC-Vってどんなプロセッサ?」参照のこと)。
実際、ArmからRISC-Vへの乗り換えの動きも見られる。Armとしては、半導体IP分野でほぼ世界中の半導体企業と契約してしまったいまとなっては、これ以上の成長を望もうとしたら何らかのビジネスモデルの転換が必須な時期に来ているのだ。自社製品が大当たりすれば、お金を刷るがごとくに、高利益を載せた自社チップを売りさばけるというのは大いなる欲望だろう。
ただし半導体IPビジネスを止めて、一気に自社製品に切り替えるというのはあまりにもリスクが大きすぎる。特にローエンドの組み込み用途のように、一つ一つは細かいけれど膨大な顧客がいるような市場はやりたくないだろう。
具体的に言えば、「Cortex-M」シリーズや「Cortex-R」シリーズなどのコアを使っているような分野だ。この分野は圧倒的多数のライセンシー企業にビジネスをお任せした方が手離れがよい。
多数といってもカウント可能な数のライセンシー企業とだけ付き合っていれば、チャリンチャリンとお金が入ってくるからだ。この分野へ下手に自社製品など投入すると、ライセンシーをRISC-V派に追いやってしまい、結果として自分で自分の首を絞めることになりかねない。まぁ、利幅の薄いところはRISC-Vに取られても仕方ないと思って、長期的にビジネスを継続するのがベターだろう。
Armが狙う先はプラットフォーマーが最適?
しかし、プラットフォーマー相手のAI市場向け分野は異なる。この分野のプレイヤーは指折り数えられるほどの数だからだ。そのような企業相手に自社製品を販売するのは、NVIDIAがいまできている商売の規模を考えると魅力的だろう。
だいたいNVIDIAがArmを買収しようとしたといういきさつもあるし、相性は悪くない(独占禁止法などで許可が下りなかったが)。ただし、この分野のプレイヤーは社内に半導体設計能力のあるところが多い。AppleやGoogle、Amazonなどは先端半導体を内製できている(当然ながら製造はTSMCなどに委託しているが)。これらの会社は、Armが魅力のある製品をリリースしたときに購入する可能性はあるが、将来の製品に対していまからコミットはしないだろう。
ところが、今回その名が出てきたMetaについては、少々状況が異なると思う。Metaは先の会社などと比べると、社内の半導体開発体制は後発に思える。前回もAIアクセラレーターを内製化するためにベンチャー企業の買収を検討している、といった話があることにちょっと触れた(頭脳放談「第297回 NVIDIA一強がプラットフォーマーのAIアクセラレーター開発を加速させる?」)。現在、急速に半導体の開発体制を強化しているようにも思える。
それに関連して、Meta向けの製品をArmが「作る」というのはあり得る話だ。ただ「作る」といっても、Meta向けの製品設計までに止めて、実際の量産品はMetaがファウンドリに発注するというスタイルならば、いままでと変わらぬ半導体IPビジネスである。
一方、Armが量産品の製造にも責任を持ち、Metaを含めた顧客に汎用(はんよう)品を販売するというスタイルならば、ビジネスモデルの大変更である。いずれにせよMeta向けのカスタム度合が強いほど既存の半導体IPビジネスとの整合性は高く、多くのライセンシーからの反発なくビジネスできるだろう。逆に汎用品として売り出すとなれば、主としてハイエンド製品にArmコアを使っているライセンシーから反発や警戒の動きが出てくるに違いない。
既存ビジネスへの悪影響なく自社製品化するとすれば、Metaを含めた取引先の数と用途はなるべく少なく、それでいてインパクトが大きいプラットフォーマーを相手にする方がよい。ArmのAI分野におけるプレゼンスは大いに上昇するだろう。
筆者の個人的な意見だが、AIデータセンター用途はよいけれども、スマートフォン用途などはとってもマズイと思う。既存ビジネスの足を引っ張る影響がすぐ出るわりには、実際にお金になるまでの時間がかかると予想するからだ。下手すると「あぶ蜂取らず」で赤字になりかねないと思う。株価に対するインパクトを考えてもスマートフォン向けではなく、AIデータセンター向けでないとならないだろう。
まぁ、いずれにせよ、製品が出る前にはArmから公式の発表があるだろう。もしかすると、FTの勇み足で公式にならずに終わる可能性だってある。とはいえ、Armにしたら転換期に差し掛かっているのは事実だし、それが2025年のアクションとなって目に見えることになるのだろう、と期待している。
筆者紹介
Massa POP Izumida
日本では数少ないx86プロセッサのアーキテクト。某米国半導体メーカーで8bitと16bitの、日本のベンチャー企業でx86互換プロセッサの設計に従事する。その後、出版社の半導体事業部などを経て、現在は某半導体メーカーでヘテロジニアス マルチコアプロセッサを中心とした開発を行っている。
Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.