
 |
「場所貸し」から柔軟な「インフラ」へ クラウド時代を前に変わるデータセンターの役割 |
| 顧客ニーズやサービスの拡大に合わせて迅速にサーバを増設したい、だがそれらの設備を社内に置いて運用するとなると荷が重い……そう考える企業にとって有力な選択肢が、データセンターへのアウトソーシングだ。「手元に置く方がいざというとき安心だ」という考え方もあるだろうが、データセンターには、自社内にスペースを用意してサーバを設置する場合には実現しにくい、いくつかのメリットがある。 |
| 「場所貸し」から企業を支える「インフラ」へ | ||
データセンターという事業形態が注目を浴びるようになったのは、ブロードバンドサービスが普及し始めた数年前。Webサイトを開設し、オンラインショッピングサービスなどを展開する企業が相次いだ、言うなれば「Web 1.0」の時代のことだ。サーバの設置や運用を自社で行う場合に比べ、高品質のファシリティや接続環境を安価に入手できる点がメリットだ。
具体的なサービスとしては、自社が保有するサーバをそのまま事業者に預かってもらう「コロケーション(ハウジング)」が挙げられる。それに付随して、以下のようなサービスメニューが提供されることが一般的だ。
|
また多くのデータセンター事業者では、サーバやOS、その上で動作するアプリケーションなどをパッケージ化して顧客に提供する「ホスティング」もメニューに加えている。検証された環境を安価に利用できることがメリットだ。さらに、死活監視だけでなくより高度な運用管理サービスを組み合わせた「マネージドサービス」、不正侵入の防止や拠点との安全な接続を提供する「セキュリティサービス」など、ニーズに応じてさまざまなメニューが加わり、いまに至っている。
現在では、ハードウェアや回線(帯域)のコストが大幅に下がり、サーバを自社で保有するのもそう難しいことではなくなった。だが、サーバ群は企業ビジネスを支える要であり、インフラだ。それだけに、それを預かるデータセンターの役割も、改めて重視されるようになっている。
| データセンターに求められる条件とは | ||
基本は「スペース貸し」なのだから、コストだけでデータセンターを決められるかというとそうはいかない。オンラインでさまざまなビジネスを展開する企業はもちろん、社内向けのアプリケーションやサービスを展開する企業にとっても、サーバやそこに格納されたデータは生命線だ。安定して運用されなければ、即、ビジネスに支障が生じることになる。そうした事態を避けるために、データセンターが最低限満たすべき条件を見ていこう。
| 関連記事: | |
| データセンター活用術(@IT Master of IP Network) http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tokusyuu/05datacenter/datacenter01.html |
|
| データセンターの利用をいつ、どう判断するか(@IT 情報マネジメント) http://www.atmarkit.co.jp/im/cop/serial/dcknowhow/01/01.html |
|
■信頼性
まず真っ先に挙げられるのが、信頼性の高さだ。データセンターはたいていが専用の建物の中に設定されており、大量のサーバの需要に応えうるだけの電源や空調、回線設備といったファシリティが充実している。
電源については、直流(DC)か交流(AC)か、電圧はいくつかといった基本的な条件に加え、複数系統確保されているか、また停電などの非常に備えた発電機やバッテリーが用意されているかなどがポイントだ。空調にしても、ラック当たりの冷却能力はどのくらいで、排熱のための「ホットアイル」と冷風を流す「コールドアイル」がどのように配置されているか、エアフローの流れを確認することになる。空調機器そのものにも冗長性が必要だ。
そもそもデータセンターは、立地条件からして、地震や水害のリスクが少ない場所に置かれることが多い。さらに、建物や土台の耐震構造はどうなっているか、万一火災が発生した場合の消火システムや耐火性はどうなっているかもチェックすることになる。
こうした条件を満たしたスペースをオフィスビルの一角に設置しようとしても、かなりの困難が伴うだろう。まず、24時間安定した電源を確保することが難しい上に、建物の構造が異なり、床などの補強が必要になることもある。高額の投資を行わなければ、大量のサーバを確実に運用できる環境は整えにくい。
ちなみに、日本列島は地震や水害といった災害に見舞われることが多い。データセンター側である程度耐災害設備を整えていても、影響を免れない可能性がある。そうしたケースに備え、データセンター自体がメインとサブの2つの施設を用意し「災害対策」(ディザスタリカバリ)体制を整え、ユーザーにサービスとして提供しているケースもある。重要なデータについてはバックアップを取得、保管しておくメニューをそろえる事業者もあるので、一考の余地があるだろう。
ただ、災害対策を重視するあまり、データセンターがあまりに不便な場所にあっては困る。トラブルや万一のときに担当者がなるべく迅速に駆け付け、対処できる「アクセス性」もある程度確保しなくてはならない。自社が求めるサービスレベルに基づいて、このバランスを見極めることが重要だ。
■セキュリティ
重要な資産であるサーバを預ける以上、その保護も欠かせない。データセンターには、いわゆる「ITセキュリティ」だけでなく、物理的なセキュリティの確保が求められる。
まず、施設そのものへの不審な人物の侵入を排除することはもちろん、鍵や生体認証を用いた入退室管理、持ち物検査、ラックごとの管理などが実施されることが一般的だ。必要に応じて機器の出し入れを柔軟に行いながら、「共連れ」を防止する機構を設けているデータセンターもある。また、非常に重要なサーバを預ける場合は、監視カメラを通じて常時監視を行うといったオプションもあるだろう。
同時に、ITセキュリティ対策についても考慮すべきだ。ファイアウォールやIDSなど、DDoS攻撃や不正侵入、ウイルス発生時に備えた対策が用意されているかはもちろん、万一攻撃やセキュリティ侵害が発生した際の緊急対応・連絡体制はどうなっているかもポイントとなる。
■運用性
インフラ・場所貸しだけでなく、その上でサービスやアプリケーションが確実に提供されているかどうかを監視し、運用を手助けするメニューも用意されている。
基本的な死活監視にはじまり、障害監視やパフォーマンス監視といったマネージドサービスを提供している事業者は多い。さらに、ネットワーク機器も含めた運用やバッチ処理、障害対応、変更管理など、よりシステム運用に踏み込んだサービスもあり、コンサルティングとともに提供されている。この場合、ITILに沿った標準的な運用を特徴として掲げていることもある。また最近では、内部統制の観点から求められるログの取得・保管などもメニューに加わっている。
| これからのデータセンターに求められる要素は? | ||
■拡張性
ビジネスにはスピードが求められるし、季節要因による変動が生じることも珍しくない。そうしたニーズに応じて、サーバや回線といったリソースを迅速に追加できる柔軟性も重要な要素だ。
とはいえ、これまで処理能力を高めようとすると物理的にサーバを増強するしかなく、「空きラックがない」ことを理由に増設を待たされることもあった。これがデータセンターに対する不満の1つとなっていた。
この問題をうまく解決してくれそうな技術が「仮想化」である。サーバのCPUやメモリ、ディスク、あるいはネットワークといったさまざまなリソースを仮想的に1つの「クラウド」にまとめて提供することで、急に大きな処理能力が必要になった場合でも、必要な分だけを提供できる仕組みが整う。これにより、顧客のコスト削減が可能になるだけでなく、電力消費を抑え、省エネルギーにもつながると期待されている。
さらに一歩進んで、企業がデータセンターをSaaSの基盤として活用できるようなサービスも始まりつつある。自社でSaaSを展開しようとすると大規模なインフラが必要になるが、それをデータセンターが肩代わりし、自社が得意なサービスやアプリケーションをその上で展開するというイメージだ。
| 関連記事: | |
| 5分で絶対に分かるサーバ仮想化(@IT Server & Storage) http://www.atmarkit.co.jp/fserver/articles/fivemin/virtualization/00.html |
|
| ネットの進化で広がるSaaSとエンタープライズ2.0(@IT リッチクライアント & 帳票) http://www.atmarkit.co.jp/fwcr/special/interop2008/interop2008_1.html |
|
■省電力
2000年前後に導入された機器が老朽化し、リプレースの時期を迎えようとしているが、ここでもやはり仮想化が注目を集めている。データセンターに置かれていた大量の機器を仮想化技術を用いて統合、集約することにより、サーバの利用率を高め、投資効果を高めることができる。
だが集約が進み、数年前には考えられなかったような密度でサーバが設置されるようになれば、その分、電力消費や排熱も増える。そこで、各機器の省電力化・省エネルギー化――グリーンITがクローズアップされるようになった。サーバやそこに搭載されるCPU、HDDやディスクといった各コンポーネントレベルで低消費電力化が図られるとともに、サービスを継続させながら、不要なときは電力消費を抑えるための工夫が凝らされている。同時にデータセンター側でも、温度などさまざまな要因を把握しながら、空調・送風を調整し、消費電力の全体最適化に取り組もうとしている。
◆
いずれにせよ、自社がどのようにITリソースを利用しているかを把握することがまず重要だ。どういったデータをやり取りし、どのようなユーザーに利用されるのか、重視すべきポイントは何なのかを把握することによって、どのようにデータセンターを使うべきかが見えてくるだろう。
提供:ヤマトシステム開発株式会社
アダプテックジャパン株式会社
EMCジャパン株式会社
シマンテック株式会社
企画:アイティメディア 営業本部
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2009年1月16日
ソリューションFLASH Pick UP!
クロネコデータセンター
ヤマトシステム開発
 ヤマトシステム開発は「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸のコンピュータ部門に起源を持ち、ヤマトグループの ITシステムを30年以上に渡って支え続けてきた。全国にきめ細かなネットワークを持つヤマト運輸のITシステムへ求められる要件に応える過程で蓄積された、さまざまなノウハウを活かし、ユニークなサービスを展開する。
ヤマトシステム開発は「クロネコヤマトの宅急便」で有名なヤマト運輸のコンピュータ部門に起源を持ち、ヤマトグループの ITシステムを30年以上に渡って支え続けてきた。全国にきめ細かなネットワークを持つヤマト運輸のITシステムへ求められる要件に応える過程で蓄積された、さまざまなノウハウを活かし、ユニークなサービスを展開する。
Adaptec RAID 5シリーズ、2シリーズ
アダプテックジャパン
 2007年に「グリーンIT推進協議会」が設立されるなど、国内でもITの省エネ議論が活発になっている。しかし実はそれ以前から、商用データセンターや企業のデータセンターでは省電力が重要な課題だった。サーバやストレージの台数は増やさざるを得ないものの、データセンターでの電源供給には上限があり、その範囲内に納めるのが担当者にとっての頭痛の種だったのだ。ITの省電力については、これまでシステム全体で電力消費を抑えるというアプローチはあったが、それなりのコストを伴うことが導入の阻害要因となっていた。しかしアダプテックは、オープンな省電力技術により、「コストの掛からない省エネ」を実現する。
2007年に「グリーンIT推進協議会」が設立されるなど、国内でもITの省エネ議論が活発になっている。しかし実はそれ以前から、商用データセンターや企業のデータセンターでは省電力が重要な課題だった。サーバやストレージの台数は増やさざるを得ないものの、データセンターでの電源供給には上限があり、その範囲内に納めるのが担当者にとっての頭痛の種だったのだ。ITの省電力については、これまでシステム全体で電力消費を抑えるというアプローチはあったが、それなりのコストを伴うことが導入の阻害要因となっていた。しかしアダプテックは、オープンな省電力技術により、「コストの掛からない省エネ」を実現する。
最新ストレージ技術を活用した、データセンター省電力化アプローチ
EMCジャパン
 データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。
データセンターでは、企業活動を支えるITインフラの設置場所として高度な信頼性や耐障害性が求められるのは当然だが、それに加えて現在では、高度な効率性も求められるようになってきている。信頼性を高めるためにはコストに糸目は付けない、などと言える状況ではなくなってきているのだ。データセンターに設置される機器の主役とも言えるサーバとストレージに関して、EMCは仮想化を初めとするさまざまな最新技術を導入することで高度な効率性を実現する。
Veritas NetBackup 6.5 for VMware
シマンテック
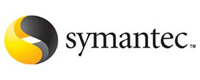 データセンターを検討するとき、もう仮想化を無視することはできないだろう。サーバ使用効率向上を狙える仮想化だが、物理サーバと同じバックアップ手法でいいのだろうか? シマンテックの答えは「NetBackup for VMware」にある。
データセンターを検討するとき、もう仮想化を無視することはできないだろう。サーバ使用効率向上を狙える仮想化だが、物理サーバと同じバックアップ手法でいいのだろうか? シマンテックの答えは「NetBackup for VMware」にある。
Veritas Storage Foundation
シマンテック
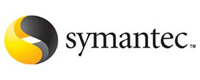 現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。
現在ではサーバの仮想化が注目を集めているが、技術の成熟度合いとしてはサーバの仮想化よりも「ストレージの仮想化」の方が先行している面がある。仮想化機能を備えたストレージハードウェアも各種販売されているが、機種ごとの機能がまちまちだったり、手持ちの古いストレージデバイスが取り残されてしまったりといった問題が生じる可能性もある。広範な種類のハードウェアをサポートできる、ソフトウェアによる仮想化のメリットに、あらためて注目が集まる。
ホワイトペーパーダウンロード
そのバックアップシステム、万一のとき本当に事業を継続できますか?
事業継続計画(BCP)への取り組みは、今やあらゆる企業にとって避けて通れない課題だ。特に情報システムの観点では、効果的なデータバックアップ体制を構築できるかどうかが重要なポイントになる。
既存システムにあるHDDの消費電力を最大70%削減する手段
(グリーンITテクノロジーセミナー資料および技術文書)データセンターで稼働しているHDDは24時間365日、1つ1つが電力を消費し続けている。その消費電力や冷却コストは無視できない。それらを最大70%削減できる施策を紹介する。
データセンター移転/統合を最小限のリスクで実施するためにすべきこと
データセンター移転/統合やグリーン化など、次世代を見据えたデータセンターの構築を最小限のリスクで行うにはどうすればよいのか。
コスト削減とITガバナンス強化を同時実現! 情報インフラストラクチャ全体最適化
コスト削減とITガバナンスの強化を両立させるのは難しい。この2点を同時実現するためには情報インフラストラクチャの全体最適化を行うのが最も近道となる。
一筋縄ではいかない、VMware仮想化環境でのバックアップとリストア
いざサーバ仮想化技術を導入しても、仮想マシンのバックアップとリストアをどのように行えばいいのか、悩んでいる企業は多いのではないだろうか。本ホワイトペーパーでは、そのベストプラクティスを示す。
シンプロビジョニングを用いたストレージ戦略成功の秘策
シンプロビジョニングストレージを採用する企業が増えつつある。データセンターで運用タスクを単純化し、かつ設備投資を節約するためにどのような手段が必要となるのか。その秘策を紹介する。

