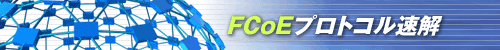FCoEの普及に向けた課題
FCoEの普及に向けた課題
- - PR -
では、CEE/FCoEが普及するうえで、どのような課題があるのだろうか? 最近、CEE/FCoEが登場することでSANもLANも一気に統合され、すべてのネットワークが簡単に1つになる、というような話を聞くこともある。が、決してそうではない。CEE/FCoEはネットワーク技術というよりも、まずはI/O統合の技術であり、特にサーバ側のI/Oを統合する技術としての利用が先に進むだろう。サーバ側インターフェイスやネットワーク機器としての入れ替えはある程度想定はつくが、ストレージ側のインターフェイスまで変わるということになると、データ移行など考慮すべき点も多くなる。これまでにも説明してきたが、ファイバチャネルを主流とするデータI/OとIPでは必要とされるネットワーク特性が異なり、さらに現状CEEはデータセンタ内で使用される技術であるので、ストレージネットワークとIPネットワークを1つのネットワークにすることは容易には実現されない。
CEEのネットワークインフラとしての管理は既存のイーサネット管理の延長として行うことが可能で、サーバ・ストレージとしては既存のファイバチャネルの管理をそのまま使用することができる。しかし、まだここには大きな問題がある。それは、「統合された物理インフラを誰が管理し運用するか、サーバ/ストレージ管理者かネットワーク管理者か?」という問題である。一般的に企業の情報システム部門ではサーバ・ストレージ管理者とネットワーク管理者が別々の業務を行っている。そもそも、運用・管理対象が異なり、ネットワークとしての特徴や運用・管理における技術スキルやツールも異なるため、それぞれの部門の責任分界点や障害時の切り分けポイントもある程度はっきりしている。 また、SANとLANと個別のネットワークがあったからこそ、そこで自然と可用性が維持されていたことも考慮しておく必要がある。
FCoEの普及を阻害する要因
- コスト&技術的成熟度
新しい技術の導入で、実際の導入・運用コストが本当に下がるのか?
10Gイーサネットのポート単価 vs 8Gbps FCのポート単価 - 組織間の壁
サーバ/ストレージ管理者とネットワーク管理者のどちらが管理するのか? - セキュリティ上の懸念
IPを通せるリンクにストレージデータを通して大丈夫か? - 既存FC投資とFCの技術革新
FC 16Gbps標準化、仮想化、サービスレベル管理
FCoEの普及を加速させる要因
- 統合への要求
初期投資、運用管理コスト、低消費電力 - 10Gイーサネットの性能ならびに普及
I/O統合に対応可能な帯域の確保 - ブレードサーバの統合ならびにサーバ仮想化
サーバ集約に追従する形でネットワーク集約 - SAN管理フレームワークの踏襲
習得した技術、ノウハウの利用
CEE/FCoEについては、技術的な課題よりも政治的な課題をどのように解決していけるかが、この技術の普及速度を左右すると考えられる。
 FCoEの導入フェイズ
FCoEの導入フェイズ
現時点では標準化は終わっていないが、導入が本格化した場合のネットワークトポロジーはどのようになるのだろうか? 特にストレージへのI/Oという観点でいえば、現状のストレージエリアネットワークとしてはファイバチャネルとiSCSIの2つの技術がある。iSCSIの場合、既存のイーサネットインフラが使用できるとはいえ、重要なデータを通すことを考えると、セキュリティとパフォーマンスの両方の観点から、一般的にはデータパスとして独立したネットワークを構築している。また、iSCSIでは先に述べたとおり、新しい管理フレームワークが必要となるため、すでにファイバチャネルSANを導入している企業では、ネットワークとしてもサーバ・ストレージ管理としても、FC SANとiSCSI SANを別々に管理する必要が出てくる。
しかし、FCoEでは既存FC SANと同様の管理スキームで対応できるので、統合管理、インフラの集約・統合ならびにバックアップやセキュリティを考慮したデータの一元管理の観点からも、わざわざネットワークとしても独立したFC SANとFCoE SAN(とでもいうべきか)を別々に管理する必要性はあまり見当たらない(もちろん試験導入環境などでは異なる。図3.1)。また、FCoEのターゲットデバイスが一般的に市場に導入されるまでは少し時間がかかると予想されていることからも、初期の導入形態としては既存FC SANのブリッジとしてFCoEを導入することで、既存FC SANの投資をそのまま活かすことが可能となる(図3.2)。さらにFCoEターゲットデバイスのリリースや、バックボーンでのFC/CEE/FCoEへの対応、それと並行して先に述べた課題が徐々に解決されれば、より一層ネットワークの統合が進むと予測される(図3.3)。CEEだけをとってみると、今後は上位プロトコルとしてFCやIPを通すだけの役割としてだけでなく、現状InfiniBandなどが使用されているクラスタ・インターコネクトなどサーバ間通信としての使用も期待される。
 |
| 図3 FCoEの導入フェイズ(クリックで拡大します) |
それでは、現状のiSCSIのような小規模なエントリレベルの構成としてのFCoEの導入はどうであろうか? 先にも説明したが、FCoEではiSCSIの導入で使用されている既存イーサネットではなくCEEが必要となるため、現状はiSCSIのような廉価なソリューションにはならない。10Gbpsイーサネットの導入に拍車がかかる事でCEEのコストダウンにつながれば、エントリレベルでの使用も期待される。しかし注目すべき点は、FCoEはiSCSIと比較してI/O処理能力上のオーバヘッドとなるTCP/IPを必要とせず、SCSIプロトコルをイーサネット(CEE)の上に直接通せることである。
 今後の動向
今後の動向
CEE/FCoEに関しては、まずは標準化が終わり、標準に準拠した製品がリリースされることが先決であるが、当初はミッドレンジサーバとブレードサーバでの対応が進むといわれている。特にブレードサーバにおいてCEE/FCoEに対応したメザニンが採用されるようになれば、いままでFCとイーサネットで個別に実装されていたメザニンならびにブレード内蔵のスイッチも集約できるため、さらにブレードサーバの集積度向上に貢献できる。また、導入にあたってはサーバ・ストレージ管理者とネットワーク管理者がはっきりと分かれている一般企業よりも、サーバ/ストレージならびにネットワークを一括して管理しているサービスプロバイダなどでの導入の方が、敷居が低くメリットも明確なため先行されるであろう。
一方、FCにおいては現状、約3〜4年で次世代の速度へと移行しており、現在8Gbps製品が出始めてきているが、すでに16Gbpsの標準が始まっており、これまでと同程度のサイクルで市場に出てくるものと予想される(図4)。
 |
| 図4 FC、CEE、FCoEの今後のタイムライン(クリックで拡大します) |
これまで3回にわたりCEE/FCoEについて説明してきたが、データセンタインフラの集約・統合が進むなか、サーバI/Oの集約を担うCEE/FCoEの今後の動向に引き続き注目していただきたい。
2/2 |
| Index | |
| FCoEをめぐる課題と未来 | |
| Page1 FCoEの構成と管理 |
|
| Page2 FCoEの普及に向けた課題 FCoEの導入フェイズ 今後の動向 |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|