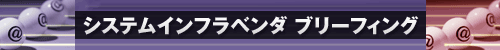
システムインフラベンダ ブリーフィング(1)
EMCとクラウド・コンピューティングの関係
三木 泉
@IT編集部
2008/9/4
 ストレージはビジネスの一要素でしかない
ストレージはビジネスの一要素でしかない
実は、前ページの高橋氏のクラウド・コンピューティングとITインフラ・サービス事業に関する発言は、EMCにおける今後の事業戦略に関連して出てきたものだ。EMCがソフトウェアやソリューションに力を入れているのは周知の事実だが、高橋氏は同社の取り組み方には、他社と決定的な違いがあると話す。
ほかのベンダとの決定的な違いを1つ言わせていただけるならば、私たちはハードウェアを一つのエレメントとしか考えていない。
システムベンダの場合はサーバ、そしてSIとのつながりでの(ストレージ)ハードウェアという位置付けなのだろうが、私たちはSIをやらず、サーバも持たずに「エンタープライズ・ストレージ・カンパニー」というところからスタートした会社だ。私たちがお客様に提供できる最大の価値は、ITインフラの全体最適ということになる。
これには、情報の生成から活用、複製、再利用、廃棄といった情報ライフサイクルマネジメントの時間軸と、ライフサイクルの節目節目でどういう処置をするか、手段を講じるかという垂直軸の全体最適がある。これらを考えた上で、できればEMCのストレージを使ってもらいたいが、他社のストレージを活用することもある。
つまり、お客様が業務アプリケーションをITのシステムとして構築する際に、情報インフラはどうあるべきなのかをシステムインテグレーションの段階から提案していく。そのなかでストレージを売っていく。他社との違いはそこに尽きる。
しかし、それは極端な話、アプリケーションから入っていくことにはならないのだろうか。現に、Documentumはそれ自体が情報管理アプリケーションといえる。
それとは違う。データ管理の運用面でどのような問題を抱えているかを聞くと、だいたいどのお客様も共通だ。業務ごとにデータがばらばらになっているから、他の業務のデータを活用しようと思ってもできないとか、ストレージの運用方法がストレージベンダによってばらばらなので、専門の業者が必要だとか、バックアップに時間が掛かりすぎて、翌朝の業務開始に間に合わない可能性があるかもしれない、などだ。そういう問題をなおざりにして新しい業務を一生懸命導入しているのが現状だ。私たちはアセスメントを提供し、「今回はこの部分の改善を踏まえた上で新しい案件を進めていったらどうですか」といったアプローチをしている。
こうしたアプローチは米国では大きな成果を上げているようだが、日本でそのまま通用するというわけではないという。
 |
米国の場合は導入する側のIT部門の人々が相当な技術力を持っているし、IT部門自体が会社のなかでも相当高い地位にある。米国ではCIOはナンバー2やナンバー3のポジションだ。だから導入する側が何をすべきかを分かっている。SIに丸投げせずに、SI業者は業務システムの構築だけやれ、サーバベンダはこれ、ネットワークはこれ、ストレージはこれということをやる。水平的に調達して、それを組み合わせるのを別の設計屋を使ってやらせるとか。(建設でいえば)自分はコンストラクションマネジメントをやるというのと同じだ。EMCが米国で一番大きなシェアをとっているのにはそういう背景がある。
日本ではSI業者に丸投げせざるを得ない企業が多い。その理由は幹部クラスになると、(IT部門長も)総務、経理などと同様に異動のポジションの1つのような位置付けなので、思い切った改革ができないからだ。従って、思い切った改革のためのスタッフィングもできない。IT部門そのものにミッションを持たせていない。外注に運用を丸投げしている場合、その原価が分からないことも多い。
(EMCとしての課題は、)こうしたビジネス慣行に対して、本来どうあるべきなのかを伝えることにある。日立も富士通もIBMも、SI案件をやっていく際に全体最適を提案する。しかし大手のユーザー企業は複数のベンダと付き合いがある。(全体最適をやろうとしても、)どれか1つのベンダのストレージに統合しようと思った時にほかとつながらない、といったことが起こる。物理的に無理が生じて残ってしまう。
ストレージだけを取り上げて、どれだけいいとか、どれだけ安いとか言い出しても、問題の解決にはならない。コンプライアンス一つをとってみても人事、経理などすべてに網をかけなければならない。これはNECのシステム、これはIBMのシステム、ここはSI業者の仕様など、マルチベンダの仕組みでコンプライアンスを担保するのは大変だ。(ユーザー企業では、)根本的な問題を解決しなければ要求に応えられなくなってきている。
幸い、われわれが現在ハイタッチ営業で出入りしているお客様は、IT部門の力が強い。従って私たちの話に理解を示していただける。業務システムはマルチベンダだが、ストレージはEMCを選択しているなど、ほかのお客様に比べると、米国のモデルに近い状態になっている。このモデルを広げていくことが一番の課題だ。 私たちの成功しているモデルをいかに広げるか、パートナーに私たちの手法を移転しながら、われわれ自身では手の届かないお客様にどうアプローチしていくかを考えていく必要がある。
では、EMCとして、ユーザーに分かってもらうために、どのような具体的アクションを進めているのだろうか。
社外に向けては、1つは営業的、マーケティング的にそういうものを広げていくこと、2つめはコンサルティング力を高めていくこと、そして3つめとしては、多かれ少なかれ大手のSIベンダが入っているので、その人たちに私たちの価値を認めてもらうことが重要だ。
製造業(のユーザー企業)は理解が早い。海外展開するときにSLAを確保しなければならない。国内で使っている仕組みを、必ずしも海外に使えるとは限らない。そうすると、発想として国内の縛りが解けてきて、海外でも使えるものを使いましょうということになる。製造業、大企業では(EMCのアプローチが)浸透しつつあるといえる。 その一方で、EMCのオファリング、特にソフトウェア寄りでは情報のそれぞれのライフサイクルに最適な製品の品ぞろえやソリューションの厚みをどのメーカーより増していって、言っていることと提供できることとの一致性をとっていく。これに関してはどのベンダにも負けない。情報ライフサイクルにおける縦軸の厚み、これはわれわれの商品力の強みであり、これをさらに増やしていく。
商品力の話をすると、大規模導入向けから中堅・中小規模導入向けまで、性能、価格、管理の容易さ、使いやすさを引き上げていきたい。製品コストだけでなく、われわれは「コスト・フォー・ソリューション」といっているが、一番安い100〜200万円クラスのストレージだと、サーバ4台とか8台ならスイッチなしでSANを構成できるとか、iSCSIだったらファイバチャネルは要らないなど、IPインフラを考えた時にコストがさらに下がるようなこともやらなければならない。、単一のコンセプトを、大企業から中堅、中小企業とさらに小さいところに広げていくのは重要な戦略の1つだ。
2/2 |
| Index | |
| EMCとクラウド・コンピューティングの関係 | |
| Page1 クラウド対応ストレージの戦略的な意味 |
|
| Page2 ストレージはビジネスの一要素でしかない |
|
- Windows 10の導入、それはWindows as a Serviceの始まり (2017/7/27)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者向けに、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能について解説していきます。今回は、「サービスとしてのWindows(Windows as a Service:WaaS)」の理解を深めましょう - Windows 10への移行計画を早急に進めるべき理由 (2017/7/21)
本連載では、これからWindows 10への移行を本格的に進めようとしている企業/IT管理者に向け、移行計画、展開、管理、企業向けの注目の機能を解説していきます。第1回目は、「Windows 10に移行すべき理由」を説明します - Azure仮想マシンの最新v3シリーズは、Broadwell世代でHyper-Vのネストにも対応 (2017/7/20)
AzureのIaaSで、Azure仮想マシンの第三世代となるDv3およびEv3シリーズが利用可能になりました。また、新たにWindows Server 2016仮想マシンでは「入れ子構造の仮想化」がサポートされ、Hyper-V仮想マシンやHyper-Vコンテナの実行が可能になります - 【 New-ADUser 】コマンドレット――Active Directoryのユーザーアカウントを作成する (2017/7/19)
本連載は、Windows PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は、「New-ADUser」コマンドレットです
|
|




