|
最新チップセットの機能と性能を探る 8. 実験時のテスト環境についてデジタルアドバンテージ 島田広道 |
|
ここでは、本記事で各種実験を行ったときのベンチマーク・テスト環境の詳細を記す。
グラフィックス・ベンチマーク・テストについて
2Dグラフィックスの性能を調べるベンチマークでは、テスト用PCにコンパックコンピュータのDeskpro EN C600/128/20/NWを利用している。以下にテスト用PCの主な仕様を記す。このPCの詳細については、「特集:最新のビジネス向けPCを解剖する」を参照していただきたい。
| ベンダ名 | コンパックコンピュータ |
| 製品名 | Deskpro EN C600/128/20/NW |
| プロセッサ | Intel Celeron-600MHz |
| マザーボード | コンパックコンピュータ製 |
| チップセット | Intel 815E |
| メイン・メモリ | PC133対応の128Mbytes SDRAM DIMM |
| GPAカード | 本機に標準装備のもの。容量4Mbytes |
| AGPグラフィックス・カード | クリエイティブメディア 3D Blaster GeForce2 GTS(NVIDIA社のGeForce2 GTS アクセラレータ、32Mbytes DDR SDRAMを搭載) |
| ハードディスク | Ultra ATA/66対応の20Gbytes IDEハードディスク×1台 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TXイーサネット標準装備(チップセット内蔵)。ただしテスト時は未使用 |
| OS | Windows 2000 Professional英語版 |
| 画面の設定 | 1024×768ドット、6万5536色、リフレッシュ・レート75Hz |
| グラフィックスのベンチマークに使ったテスト用PCの仕様 | |
| もともとプレインストールされているOSは、Windows 2000 Professional日本語版とWindows NT Workstation 4.0日本語版である(最初の起動時にどちらかを選択する)。またAGPグラフィックス・カードは編集部で独自に追加したもので、コンパックから提供されるオプションではない。 | |
 |
|
テストに用いたコンパックコンピュータのDeskpro EN |
2Dグラフィックスのベンチマーク・プログラムには、米BAPCo社のSYSmark 2000というアプリケーション・ベンチマークを利用した。SYSmark 2000の詳細については、「特集:x86最速プロセッサ Pentium III-1.13GHzの実像に迫る」を参照していただきたい。なお、2000年9月の時点でSYSmark 2000はWindows 2000日本語版で動作しないため、やむを得ずWindows 2000英語版をテストPC用にインストールしてSYSmark 2000を実行している。
3Dグラフィックスのベンチマーク・テストでは、コンパックコンピュータのDeskpro EN C600/128/20/NW(Celeron-600MHz搭載機)と、エプソンダイレクトのEndeavor MT-4000(Pentium III-866MHz)の両方をテスト用PCとして使用した。Endeavor MT-4000の仕様については、後述のメモリ・ベンチマークの説明を参照していただきたい。またベンチマーク・プログラムには、MadOnion社の3DMark2000を用いている。これは主に3Dゲームを利用する場合の性能を測定するためのプログラムだが、APIにはDirect3Dを用いているので、Direct3Dを多用するアプリケーションには参考となる。以下に、今回のテストで設定した3DMark2000固有の設定値を記す。
| 設定項目 | 設定内容 |
| 解像度 | 1024×768ドット、6万5536色、リフレッシュ・レート75Hz |
| Zバッファの深度 | 16bits |
| バッファリング方式 | Triple buffering |
| 垂直同期周波数と描画の同期 | オフ |
| CPUの最適化手法 | Intel Pentium III対応 |
| 3DMark2000固有の設定 | |
メモリ・ベンチマーク・テストについて
テスト用PCには、エプソンダイレクトのEndeavor MT-4000を使用した。ベンチマーク時のテスト用PCの主な仕様は以下のとおりである。なお、本機の詳細については、「特集:最新のビジネス向けPCを解剖する」を参照していただきたい。
| ベンダ名 | エプソンダイレクト |
| 製品名 | Endeavor MT-4000 |
| プロセッサ | Intel Pentium III-866MHz |
| マザーボード | ASUSTeK Computer社製CUSL2-M |
| チップセット | Intel 815E |
| メイン・メモリ | PC133メモリ:PC133 128Mbytes SDRAM DIMM×1枚 |
| PC100メモリ:PC100 128Mbytes SDRAM DIMM×1枚 | |
| グラフィックス | チップセット内蔵グラフィックス(ディスプレイ・キャッシュはなし) |
| ハードディスク | Ultra ATA/66対応の20.5Gbytes IDEハードディスク |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TXイーサネット標準装備(マザーボード上に実装)。ただしテスト時は未使用 |
| OS | Windows 98 Second Edition日本語版 |
| 画面の設定 | 1024×768ドット、6万5536色、リフレッシュ・レート75Hz |
| メモリのベンチマークに使ったテスト用PCの主な仕様 | |
| 本機はBTOによるカスタマイズが可能なので、機種名が同じでも仕様は異なることがある。 | |
 |
|
テストに用いたエプソンダイレクトのEndeavor MT-4000 |
ベンチマーク・プログラムには、2Dグラフィックスのときと同じBAPCo社のSYSmark 2000を利用した。OSは、テスト用PCにプレインストールされていたWindows 98 Second Edition日本語版を、ほぼそのまま利用している。ただし、SYSmark 2000を日本語版OSにインストールするためにキーボード・ドライバを入れ替えている。また、ベンチマーク測定のために不要な常駐プログラムを排除する、といった細かい設定変更も行っている。
USBベンチマーク・テストについて
このテストでは、4ポートのUSBを実装するPCが必要だったが、前出のテスト用PC2機種はどちらも2ポートのUSBしか持っていなかったため、別途、以下のようなテスト用PCを用意した。
| プロセッサ | Intel Pentium III-667MHz |
| マザーボード | AOpen社製AX3S Pro |
| チップセット | Intel 815E |
| メイン・メモリ | PC133対応の128Mbytes SDRAM DIMM |
| グラフィックス | チップセット内蔵グラフィックス(ディスプレイ・キャッシュはなし) |
| ハードディスク | Ultra ATA/66対応の30Gbytes IDEハードディスク |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TXイーサネット標準装備(チップセット内蔵)。ただしテスト時は未使用 |
| USB | チップセット内蔵ホスト・コントローラ(ルート・ハブ)×2、ポート数は4 |
| OS | Windows 2000 Professional日本語版 |
| 画面の設定 | 1024×768ドット、6万5536色、リフレッシュ・レート75Hz |
| カード・リーダ | ウエップシステム製FilmPort USB |
| イメージ・スキャナ | セイコーエプソン製GT-7600U |
| USBのベンチマークに使ったテスト用PCの主な仕様 | |
テストの方法は、USB接続のカード・リーダ(下の写真)に挿入したコンパクト・フラッシュのATAフラッシュ・メモリから、サイズが44Mbytesのファイルを読み出しつつ、同時にUSB接続のイメージ・スキャナ(下の写真)でもA4原稿をスキャンし、71Mbytesのデータを読み出す、というものだ。両方ともデータ転送が始まってから、PCがその処理から解放されるまでの時間をストップウォッチで計測し、データ容量をその時間で割ることで平均転送レートを得ている。グラフに記したのは、このように計算された平均転送レートである。なお、カード・リーダとイメージ・スキャナの両方とも、ファイルやデータのサイズを変更したりすると、この平均転送レートは変動した。つまりグラフに示した値が、これらの製品の最大性能ではないことに注意していただきたい。![]()
 |
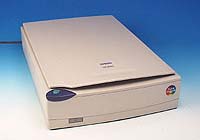 |
| テストに用いたカード・リーダ(左)とイメージ・スキャナ(右) | |
| カード・リーダ(左)には、ウエップシステムのFilmPort USBという製品を使用した。PCカードとスマート・メディアそれぞれのスロットを装備している。またイメージ・スキャナ(右)には、セイコーエプソンのGT-7600Uという製品を使用した。A4サイズの用紙をカラーでスキャンできる。 | |
| 関連記事 | |
| 最新のビジネス向けPCを解剖する | |
| x86最速プロセッサ Pentium III-1.13GHzの実像に迫る(SYSmark 2000の説明) | |
| カード・リーダなどその他周辺機器ベンダのリンク集 | |
| スキャナ・ベンダのリンク集 | |
| 関連リンク | |
| Deskpro ENの製品情報 | |
| Endeavor MT-4000の製品情報 | |
| SYSmark
2000の概要 |
|
| 3DMark2000のページ |
|
| 「PC Insiderの実験」 |
- Intelと互換プロセッサとの戦いの歴史を振り返る (2017/6/28)
Intelのx86が誕生して約40年たつという。x86プロセッサは、互換プロセッサとの戦いでもあった。その歴史を簡単に振り返ってみよう - 第204回 人工知能がFPGAに恋する理由 (2017/5/25)
最近、人工知能(AI)のアクセラレータとしてFPGAを活用する動きがある。なぜCPUやGPUに加えて、FPGAが人工知能に活用されるのだろうか。その理由は? - IoT実用化への号砲は鳴った (2017/4/27)
スタートの号砲が鳴ったようだ。多くのベンダーからIoTを使った実証実験の発表が相次いでいる。あと半年もすれば、実用化へのゴールも見えてくるのだろうか? - スパコンの新しい潮流は人工知能にあり? (2017/3/29)
スパコン関連の発表が続いている。多くが「人工知能」をターゲットにしているようだ。人工知能向けのスパコンとはどのようなものなのか、最近の発表から見ていこう
|
|





