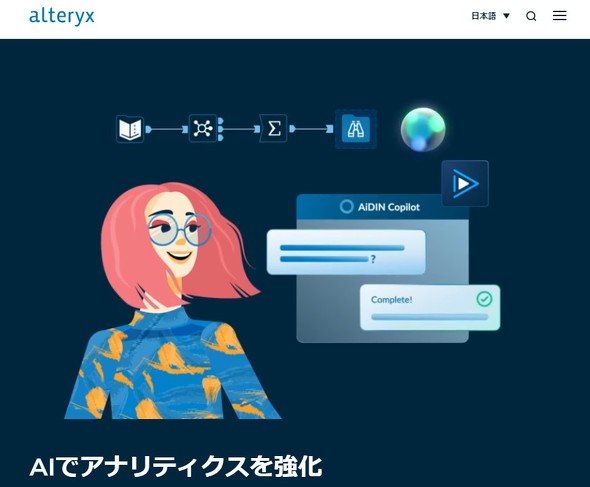試験的に生成AIプロジェクトを実施した企業の80%が「成功した」と回答 アルテリックスが調査結果を発表:企業と一般消費者で生成AIの捉え方に違い
アルテリックスは、生成AIに対する認識と心情に関する調査レポートを発表した。日本企業の77%が「生成AIはビジネス価値を高める」と回答したものの、一般消費者の3分の1は生成AIに対して懐疑的な印象を持っていると答えた。
アルテリックスは2024年5月21日、「Market Research:Attitudes and Adoption of Generative AI(生成AIに対する考え方と受容に関する市場調査)」を発表した。これは世界11カ国で、企業のデータ活用に携わるチームの意思決定者(ITビジネスリーダー)2000人と一般消費者3000人を対象に実施した調査の結果を基に、生成AIとの関わり方や導入状況についてまとめたもの。
日本では、企業の77%が「生成AIはビジネス価値を高める」と回答しているが、一般消費者の37%はその価値に懐疑的で、33%は「生成AIの将来性に懸念がある」と答えており、企業と一般消費者の間で生成AIについての捉え方に違いがあった。
半数が「生成AIで誤った情報が生成されたことがある」と回答
生成AIの利用シーンを見ると、一般消費者は「情報検索」(60%)、企業では「データ分析」(38%)という回答が最も多かった。生成AIの利用については、生成AIを利用したコンテンツの作成が増えることをポジティブに捉えている一般消費者の割合は85%。ただし、53%は「規制が必要だ」と回答した。
企業での利用実態を見ると、過去1年間で企業が試験的に実施した生成AIの関連プロジェクト数は平均して3つ。そのうち、80%が「プロジェクトは成功した」と回答した。生成AIの利用を拡大させるために解決すべき課題については「セキュリティの懸念」(41%)、「コスト管理」(39%)、「アウトプットの品質と信頼性」(37%)が上位を占めた。
一方、「生成AIで誤った情報が作成されたことがある」と回答した企業は49%。39%が「生成AIで作成された情報に著作権や知的財産権を侵害する内容が含まれていたことがある」と回答している。
アルテリックスで最高情報責任者(CIO)を務めるトレバー・シュルツ氏は、「生成AIには、信頼性や倫理的な懸念、スキル不足、プライバシー侵害の恐れ、アルゴリズムの偏りなど、克服しなければならない重要な課題を抱えている。生成AIの恩恵を真に享受するには、企業はプライバシーや偏見への懸念に対処しつつ、技術に明るくないユーザーが安全で信頼できる環境を用意する必要がある」と述べている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 なぜ新しい技術に「がっかり」してしまうのか SCSKが“AIに幻滅しないためのマインドセット”を解説
なぜ新しい技術に「がっかり」してしまうのか SCSKが“AIに幻滅しないためのマインドセット”を解説
新しい技術が注目を集めると、期待とともに「思ったほど普及しないかもしれない」と感じることがある。個人的に思うだけならいいが、技術の業務展開においては致命的な問題になり得る。組織の中で新しい技術を“当たり前の技術”にするにはどういったマインドセットが必要なのか。 最適解は「コード補完」から「自動化ワークフロー」へ? 有識者が予測する“生成AIの今後”とは
最適解は「コード補完」から「自動化ワークフロー」へ? 有識者が予測する“生成AIの今後”とは
TechTargetは「生成AIアプリケーションの動向」に関する記事を公開した。2024年に開催された「Google Cloud Next '24」では生成AIに関する多くの情報が公開された。期待が高まる生成AIアプリケーションだが、その進化は速く、それに伴う課題も生まれている。 従業員に起因するサイバーセキュリティリスクの軽減における生成AIの可能性
従業員に起因するサイバーセキュリティリスクの軽減における生成AIの可能性
データ侵害の大部分は、人的要素が関与している。生成AIは、従業員に起因するサイバーセキュリティインシデントを減らす切り札になるだろうか。