| 帳票・集計レポート出力機能は、OEM・製品連携で補完 業務アプリケーションの開発効率向上と 顧客満足の向上を両立する! |
| 業務システムのサブ機能として、重要な役割を持つ帳票・集計レポート出力。だが、ビジネス環境の変化に伴い、ユーザーがアウトプットに求める機能も変化している。一方、業務システム/パッケージベンダは、そのニーズを理解していながらも、本業のビジネスロジック開発で忙しく、なかなか手が回らないのが実情だ。こんなユーザー、開発ベンダの課題を、ウイングアーク テクノロジーズが解決する。 |
| 業務システムと帳票・集計レポート出力の「切っても切れない関係」 | ||
会計、生産管理、販売管理、購買管理、ワークフローなど、企業の中で業務を支えるシステム群。これらの業務システムと、切っても切れない関係にあるのが帳票だ。
帳票とは字のとおり、資産の流れを記録する「帳簿」と、取引ごとにその内容を記した「伝票」が合わさった言葉で、帳票を見れば、その企業のビジネスの動きや結果がすべて把握できる。そのため、総勘定元帳やキャッシュフロー計算書、貸借対照表や損益計算書など会計分野の帳票類は、法定帳票として保管が義務付けられている。
また、法定帳票の中には書式レイアウトや項目名などを、関係省庁が規定しているものもある。日本企業の場合、各社固有の帳票でも、レイアウトや文字フォント、罫線の太さまで細かく定めているケースがほとんどだ。「形式を重んじる日本文化が、こうした商習慣を育ててきた」ともいわれているが、形式が定まった帳票を使うことで、スムーズに事後処理できるというメリットもある。また昨今では、バーコードを使った物品/倉庫管理が増えたため、納品書の中にバーコードラベルを印刷し、業務改善に一役買っている例など、枚挙にいとまがない。
集計レポート機能についても同様だ。「何を、何個、いつまでに納品する」といった受発注情報、「いつ、誰が、どこから来て、どのくらいの時間ページを閲覧したか」というWebサイトのアクセスログなど、企業は日々さまざまなデータを収集している。こうした生データは業務改善のヒントが眠る宝庫だ。経営層や現業部門において「さまざまな切り口でデータを閲覧したい」といったニーズが強まっている今、集計レポート機能は欠かせない要素といえる。
以上のように、日本の商習慣や業務改善において、帳票や集計レポートが果たす役割は大きく、むしろ「業務そのものと帳票や集計レポートは、切っても切れない関係にある」と考えた方がいいだろう。あらゆる業務システムごとに、帳票・集計レポート出力システムが付随しているのも当然なのだ。
| 業務環境変化に伴い、変わる帳票・集計レポート出力へのニーズ | ||
このように、ビジネスにおいて帳票や集計レポート出力が果たす役割が大きいからこそ、環境の変化に伴い、ニーズもどんどん変化する。特に法定帳票のように、法改正に伴い帳票レイアウト自体が変化してしまうものは、都度開発しなおす必要があるため、コストがかかってしまうという問題がある。また、新しいビジネスを立ち上げたら、「帳票の商品コード桁数を変えたり、表示項目数を増やすといった手間もかかってしまった」という事態もあるだろう。
そのほかにも、例えば出力でいえば、従来のような紙印刷に加え、電子メールやインターネット、FAXで帳票を送付するケースも増えてきた。その一方で、セキュリティの脅威が年々大きくなっているという状況がある。ビジネスの重要情報が記載された帳票だからこそ、「安心・安全なファイル形式で帳票を出力したい」というニーズが高まっている。電子帳票のフォーマットとして多く採用されているのがアドビ システムズのPDFだが、昨年マイクロソフトが発表したXPS形式も徐々に浸透しつつある。こうした最新技術への対応も課題の1つだ。
もちろん最新の帳票システムを導入すれば、こうしたニーズは解決できる。しかし業務システムと密連携した帳票システムでは、業務システムごとに帳票システムを用意しなければならず、導入の手間やコスト面で多大なロスが生じてしまう。
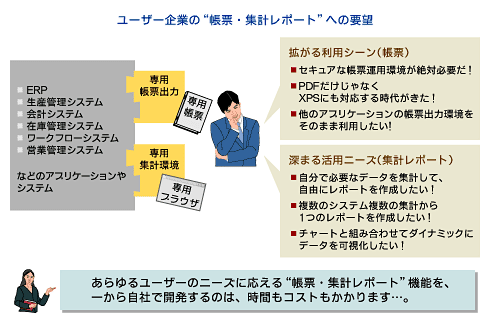 |
| 図1 帳票・集計レポート機能にはさまざまなニーズがある(クリックで拡大) |
また、業務システム固有の帳票システムでは、固定帳票だけではなく、分析を目的とした集計レポートなどの自由帳票を出力する際も、「こういう分析軸でなく、もっと詳細なレポートが必要なのに」「グラフが分かりにくい」といったように、ニーズに応え切れないことが多い。
高いコストで専用システムを導入すれば、あらゆる課題を解決することはできる。しかし、すべてのシステムに共通で使えるとは限らないのが難しいところだ。その結果、「ビジネス要件に対応できない」「使いにくい」といった不満だけが残ることになる。ユーザー側にとっては、各業務システムに共通で使える帳票システムを、1つだけ導入することが最も効率的なのだ。
| 業務システムベンダが抱えるジレンマを解決 | ||
一方、業務システムやパッケージを提供するベンダ側から見れば、細かな帳票形式の変更や項目追加に対応するより、本来の業務システム機能の刷新や強化に取り組んだ方がいい。帳票機能に関し、さまざまな出力形態やファイル形式にすべて対応したうえで、セキュリティ要件や細かなビジネス要求に応えていては、本業の開発が滞ってしまう。
とはいえ、帳票がなければユーザー企業のビジネスは進まない。ユーザーが最終的に求めているものは、あくまで「帳票」であり、いくら業務システムが優秀でも、自在にデータを出力できなければ、ユーザーにとって魅力は半減してしまう。この点で、帳票機能をおろそかにはできないというジレンマがある。
そんなユーザーが抱えるニーズ、開発側が抱えるジレンマを解消する手段が1つある。業務システム開発者は、本来のシステム機能開発に注力し、帳票や集計レポート出力部分に関しては専業ベンダの製品と連携してしまうことだ。
その際、これまでのようにシステム機能と密連携させると、ユーザー側が「この出力の機能を別のシステムから使いたい」といったときに困ってしまう。ポイントは、専業ベンダの高機能なアウトプットの仕組みを自社製品に疎連携してしまうことだ。こうすれば帳票・集計レポート出力部分の作り込みに忙殺されることなく、ユーザーニーズに応えるシステムができあがる。こうした解決策を提示するのが、ウイングアーク テクノロジーズだ。
| 専業の帳票ベンダ製品ならユーザーニーズに応えられる | ||
ウイングアークの「Super Visual Formade」は、導入実績1万6000社を誇る帳票システムのデファクト・スタンダードだ。この実績の背景には、「ユーザーが求める帳票へのニーズすべてに応えている」高機能性がある。
第1に、だれでも簡単に帳票レイアウトを設計できること。プログラムレスで、複雑な帳票レイアウトでもデザインできるので、極端にいえば、ユーザー企業の業務担当者自身が帳票を設計することも可能。財務諸表、納品書や請求書など一般的なもののほか、カルテや工程管理といった、多彩な表現に対するニーズにも対応可能だ。
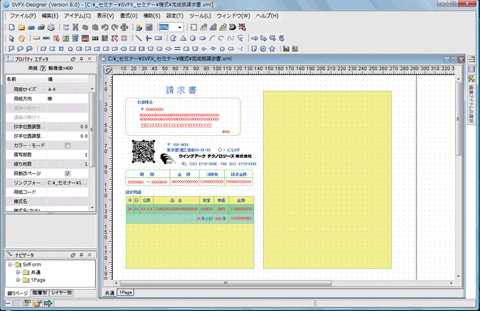 |
| SVFX-Designerの帳票作成画面例。扱いやすいUIが特長 (クリックで拡大) |
第2に、PDFやCSV、XPS、TIFFファイル出力や、FAXシステムへの帳票出力、クライアントへの直接印刷など、多用な出力形態に対応していること。このほか、大量センター出力や拠点へのバッチ配信も可能だ。
第3に、ODBC/JDBCを通じて、データベースと直接連携できること。例えば商品マスタから、商品コードや商品名を抽出し、あらかじめ定義した帳票の入力項目フィールドに、自動的にデータを入れるといった操作が可能になる。ミスが許されない帳票だからこそ、こうしたきめ細かさは重要になる。
第4に、Webシステムやデータベース、クライアント/サーバ、ERP、メインフレームなど多様な業務システムと連携できる点。ほかのシステムからSVFの出力機能を使う場合は、TXT/CSV/XMLなどの標準技術を通じて出力データを送信できるので、使い方によっては、全社共通の帳票基盤とすることも可能だ。
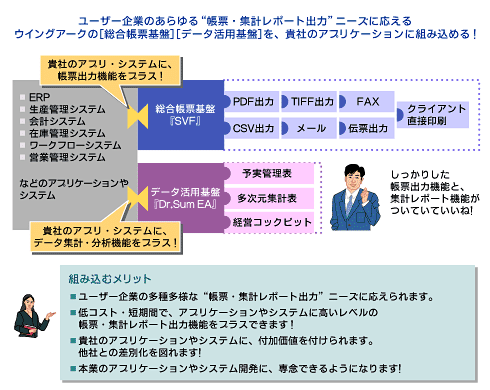 |
| 図2 SVFとDr.Sumで、ユーザーと開発者、双方の課題を解決(クリックで拡大) |
そしてもう1つ、同社が提供する高速集計・検索ツール「Dr.Sum EA」は自社が抱える業務システムと連携することができる。Dr.Sum EAは、100万件のデータ集計も瞬時に処理するという高速性を誇り、加えて分析レポート画面も、SVFと同じくノンプログラミングで開発できるので、ユーザー企業の業務担当者でも簡単に画面設計ができる。社内に存在するさまざまなデータソースも、ノンプログラミングで統合できるので、業務システムを超えた詳細集計が可能だ。
| ユーザー満足度も大きく向上 | ||
SVF、Dr.Sum EAを業務システムに連携することで、どのようなメリットがあるのだろう。まず、業務システムの帳票機能・レポーティング機能そのものの性能が格段に向上する。この部分に専業ツールのノウハウを組み込むことで、開発側は、本来のシステム機能強化に取り組めるはずだ。
ユーザー側から見れば、帳票機能もシステム機能も向上したことで、より業務生産性の向上が期待できる。また帳票やレポーティング機能を、複数のアプリケーションと疎連携し、自在に出力可能となるのは大きなメリットだ。さらに、帳票と同様のフォーマットで、より手軽かつ確実に入力したい、という要望には、帳票型画面設計を持つ入力ソリューション「StraForm -X」もあり、とことんユーザーニーズに対応できる。
ITコストの点から見れば、これまで都度依頼していた帳票・レポートの新規開発を切り替えることでコスト抑制につながる。新規ビジネス立ち上げの際にも、必要帳票を迅速に開発できることで、ビジネススピードが一段とアップする。
こうしたメリットがあるからこそ、「SVFが組み込まれたパッケージ/システムを使おう」という結論に行き着くだろう。実際、ユーザーへのこうした訴求ポイントを評価したアプリケーションベンダが続々とSVFを自社製品に組み込んでおり、ユーザーの満足度も高くなったという。
業務システムとアウトプットの機能は、切っても切れない関係だ。だからこそ、充実した帳票・集計レポート機能を組み込んだシステムは、ユーザーからの評価が高いのである。
|
提供:ウイングアーク テクノロジーズ株式会社
企画:アイティメディア 営業局
制作:@IT編集部
掲載内容有効期限:2008年6月27日
|

