|

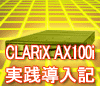 |
AX100i実践導入記
iSCSIの活用でバックアップ作業の効率化を実現する
2. CLARiX AX100iによるスナップショット作成の実践
|
ページ1 ページ2
ここからは実際にCLARiX AX100iを使ってスナップショットの作成手順を見ていくことにする。CLARiX AX100iの接続環境は、前回の「iSCSI対応ストレージ 「CLARiX AX100i」の導入でストレージ統合を目指す」と同様のものだ。
|
|
| CLARiX AX100iの接続構成図 |
|
2台のWindowsサーバとCLARiX AX100iを接続し、片側のサーバ(Main Server)にマウントされているボリュームのスナップショットを作成し、それをもう片側のサーバ(Backup Server)にマウントしてみる。 |
まず前回と同様、仮想ディスクを作成し、1台のサーバへの割り当てを行う。
|
|
| CLARiX AX100iのベア・ドライブ状態(拡大画面) |
| テストに用いたCLARiX AX100iには4台の250Gbytes SATA接続ハードディスクが内蔵されていた。ここではDisk 0〜3の全領域を使ったRAID 5アレイとして[ディスクプール1]を設定する。 |
|
|
| 仮想ディスクの状態(拡大画面) |
| 上画面で設定した[ディスクプール1]上に、200Gbytesの[Virtual Disk 01]と80Gbytesの[Virtual Disk 02]のRAID 5ボリュームを確保し、[Main Server]に割り当てを行った。 |
■スナップショットの設定
スナップショットの作成は、以下の手順で行う。
- 仮想ディスクごとにスナップショットの初期化を行う
- 仮想ディスクのスナップショット領域に対して、Navisphere Server Utilityによってスナップショットを発行する
スナップショットの初期化は、管理ツールの「Navisphere Express」を利用する。Navisphere Expressは、Webブラウザでコントロール可能となっているため、管理用ネットワーク(社内LAN)に接続されているコンピュータ(以下、管理用PC)からリモートで設定が行える。
管理用PCのWebブラウザで、Navisphere Expressを起動し、左側の[管理]−[スナップショット]メニューをクリックする。新規にスナップショットを作成するには、[スナップショットの管理]画面の[スナップショットの新規準備]ボタンをクリックする。
|
|
| スナップショットの新規準備(拡大画面) |
| Webブラウザで管理ツール「Navisphere Express」を起動し、[管理]−[スナップショット]メニューをクリックする。 |
| |
 |
ここをクリックする。 |
| |
 |
すでに設定されたスナップショットがなければ、ここをクリックして新規にスナップショットを設定する。 |
|
画面に作成済みの仮想ディスクが一覧表示されるので、ここでスナップショットを設定する仮想ディスクを選択する。さらに作成したスナップショットを割り当てるサーバを指定しておく。この割り当て作業は、仮想ディスクごとに1度行えばよい。
|
|
| スナップショットを仮想ディスクに対して設定する(拡大画面) |
| スナップショットを設定する仮想ディスクとそれを割り当てるサーバを選択する。 |
| |
 |
仮想ディスクが列挙されるので、スナップショットを設定する仮想ディスクをボタンで選択する。 |
| |
 |
プルダウン・メニューでCLARiX AX100iが認識しているサーバ名からスナップショットを割り当てるサーバを選択する。 |
| |
 |
ここをクリックすると割り当て処理が開始される。 |
|
割り当て作業は、仮想ディスクの容量によって異なる。編集部で試したところ、200Gbytesの[Virtual Disk 01]で15分程度、80Gbytesの[Virtual Disk 02]で5分強の時間がかかった。なおスナップショット作成中は、左側の[管理]−[スナップショット]メニューを再度クリックすることで、進行具合が確認できる。
作成されたスナップショットがどのサーバに割り当てられているかは、以下のようにして確認できる。
|
|
| スナップショットとサーバの対応(拡大画面) |
| スナップショットは仮想ディスクとして扱われ、自動的に「[仮想ディスク名] のスナップショット」という名称でマウントされる。上画面では、[Backup Server]からアクセスするように設定されていることが分かる。 |
以上の作業でスナップショットを作成するための準備が整ったことになる。そこで実際にスナップショットを作成し、「Backup Server」からスナップショットへのアクセスが可能であることを確認してみよう。
■スナップショットを作成する
CLARiX AX100i上でスナップショットの初期設定を終えたら実際に運用を開始する。スナップショット機能を利用することで、通常運用しているサーバ(ここでは「Main Server」)の運用を停止させることなく、別サーバを使ってバックアップが可能になる。
まず、スナップショット機能を利用するには、Main Server上で「Navisphere Server Utility for AX Series(以下、Navisphere Server Utility)」を起動する。Navisphere Server Utilityは、CLARiX AX100iのサポートCDに含まれており、スナップショットを作成するためには、事前にインストールしておく必要がある。またMain Serverも、管理用PCと同様、管理用ネットワークに接続しておく。
スナップショットを作成するには、Navisphere Server Utilityの[スナップショット タスク]の[スナップショットの開始]を選択し、次の画面で仮想ディスクを選択すればよい。これでスナップショットが作成される。ただし、この際に開いているファイルは、スナップショットに反映されないので注意が必要だ。スナップショットの作成自体は一瞬なので、利用者に事前に連絡し、お昼休みなどの時間にネットワーク・アダプタを無効化するなどして、ネットワークからサーバを一時的に切り離し、スナップショットを作成、再び接続するといった運用で回避できるだろう。
|
|
| サーバ用ユーティリティ起動画面(拡大画面) |
| Main Serverにログインし、Navisphere Server Utilityを起動する。以後、ツール上では[Main Server]はソース・サーバとして扱われる。 |
| |
 |
スナップショットを発行するには、[スナップショットの開始]を選択する。発行したスナップショットを無効にするには、[スナップショットの停止]を選択する。1つの仮想ディスクに設定したスナップショット領域に対して、複数のスナップショットを発行することはできない。 |
| |
 |
[スナップショットの開始]を選択したら、[次へ]ボタンをクリックする。 |
|
|
|
| 仮想ディスクの選択(拡大画面) |
| Navisphere Expressでスナップショットを設定した仮想ディスク([Virtual Disk 01])を[ソース仮想ディスク]として選択する。ソース仮想ディスクは、サーバがログインしているCLARiX AX100iに対して自動的に検索される。 |
| |
 |
プルダウン・メニューから仮想ディスクを選択する。 |
| |
 |
選択したら[次へ]ボタンをクリックする。 |
|
さて、スナップショットが作成できたら、それをBackup Serverにマウントして、バックアップできるようにしよう。そのため、Backup Server側で発行されたスナップショットにアクセスするよう設定する。Backup Server側でも、Main Server側と同様、設定にはNavisphere Server Utilityを用いる。[セカンダリ サーバ]の[スナップショットへのアクセス権の許可]を選択し、次の画面で仮想ディスクとマウント・ポイントを指定する。
|
|
| Backup Serverでユーティリティを起動する(拡大画面) |
| バックアップを行うBackup Server上で、Navisphere Server Utilityを起動する。以後、バックアップを行うサーバはセカンダリ・サーバとして扱われる。 |
| |
 |
セカンダリ・サーバ上での処理は、[セカンダリ サーバ]で行う。スナップショットをサーバにマウントするには、[スナップショットへのアクセス権の許可]を、マウントしたスナップショットの利用を停止する場合には、[スナップショットへのアクセス権の削除]を選択する。 |
| |
 |
[スナップショットへのアクセス権の許可]を選択したら、[次へ]ボタンをクリックする。 |
|
|
|
| 発行したスナップショットとマウントするドライブ・レターを指定する(拡大画面) |
| ウィザードは、自動的にサーバがログインしているCLARiX AX100i上の仮想ディスクを検索する。同時に、ドライブ・レターもローカルで使用されていないものがプルダウン・メニューにリストアップされる。 |
| |
 |
スナップショットを設定していない仮想ディスクも検索され、ここに列挙される。 |
| |
 |
ローカルで未使用のドライブ・レターが列挙される。 |
| |
 |
アクセスを有効にする仮想ディスクと、それをマウントするドライブ・レターを選択したら、[次へ]ボタンをクリックする。 |
|
CLARiX AX100iやサーバ間の設定がうまく認識されない場合には、Navisphere Server Utilityの[サーバ タスク]の[サーバからSPへの接続表示/更新]を選択し、サーバ情報のアップデートを行うとよい。
|
|
| Navisphere Server Utilityでサーバ情報を更新する(拡大画面) |
| ソース・サーバでの設定がセカンダリ・サーバに反映されない、あるいはCLARiX AX100iでの設定がサーバに反映されない、といった現象が起きた場合には、Navisphere Server Utilityを利用しステータスの取得・更新を行うとよい。 |
| |
 |
ここを選択すれば、CLARiX AX100iのステータスを確認し、サーバの情報を更新できる。 |
| |
 |
サーバ情報を更新する場合は、 をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする。 をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする。 |
|
これで、Backup Serverからスナップショットへのアクセスが可能になった。Backup Severにマウントしている別のネットワーク・ストレージに、スナップショットをコピーしたり、バックアップ・ソフトウェアを利用してテープ・ドライブにバックアップしたりすることもできる。この際、Main Serverには負荷がかからないため、業務時間内にバックアップ作業が行える。もちろん、何らかの理由によりMain Serverのファイルに障害が発生した場合、スナップショットをコピーすることで復旧することも可能だ。またソフトウェアの開発現場では、特定の作業ポイント(ビルド)でスナップショットを作成することで、ソース・コードの履歴管理にも応用できるだろう。
|
|
|
|
| Main Server(上)(拡大画面)とBackup
Server(下)(拡大画面)のCLARiX
AX100iのボリューム |
| スナップショット機能を利用することで、Main ServerのボリュームをBackup Serverにマウントすることが可能だ。作成されたスナップショットは、Main Serverのボリュームとは独立しているため、Main Serverのファイルが更新されても、スナップショットには反映されない。 |
| |
| ストレージ統合とスナップショット機能でストレージ管理のコスト削減 |
|
|
このようにスナップショットは、初期設定に多少時間がかかるものの、作成自体は瞬間で終わる。そのため、バックアップ・ウィンドウを気にすることなく、バックアップ作業が可能だ。またスナップショットの作成自体も、充実した管理ツールによって容易に行える。ストレージ統合を行っていれば、CLARiX AX100iですべてのサーバのバックアップ作業が可能になるので、管理者の手間は大幅に削減できる。
特にCLARiX AX100iは、シーケンシャル・アクセスに対して高い性能を発揮するような構造になっているので、バックアップ用にもう1台のCLARiX AX100iを用意し、ディスク・バックアップを行うのもよいだろう。CLARiX AX100iは、最大12台のハードディスクが搭載可能で、3Tbytesまで増設できる。ハードディスクを追加した場合、オンライン・ボリューム拡張機能によって、運用した状態でボリュームの拡張が可能だ。ディスクの空き容量が足らなくなったら、ハードディスクを追加して簡単な設定を行うだけで、容易にボリュームの拡張ができるわけだ。
このようにCLARiX AX100iには、さまざまな機能が用意されている。またiSCSIによるSANの構築にかかるコストは非常に安価なので、サーバが増えた場合でも、余分なコストをかけずにCLARiX AX100iに接続できる。サーバごとにハードディスクを増設するより、CLARiX AX100iによるストレージ統合を行った方が、投資効率や管理コストの面で有利となるケースは多いだろう。
コラム
デュアル・コントローラ構成でコントローラにも冗長性を確保 |
いくらデータをバックアップしておいても、ネットワーク・ストレージ自体が故障してしまうと、修理まで長期間に渡って業務を止めてしまうことになる。データ自体は、RAIDで保護され、1台のディスクが故障しただけならば、故障したディスクを交換し、リビルドを行うことで、運用を継続しながらシステムの回復ができる。
しかしコントローラが故障してしまうと、コントローラの交換が必要になり、コントローラの交換が完了するまでネットワーク・ストレージの運用を停止しなければならない。そこで、CLARiX AX100iには、2つのコントローラを搭載することで冗長化し、1つのコントローラが故障しても、運用の継続が可能なデュアル・コントローラ・モデルがラインアップされている。デュアル・コントローラ・モデルでは、電源が二重化されている上、電源異常が発生した場合でもコントローラのキャッシュ上のデータが失われないように、UPSがセットになっている。複数の電源系統をサポートしているデータセンターなどでは、それぞれのコントローラに別の電源系統を割り当てることで、電源障害にも対応可能だ。
|
|
| デュアル・コントローラのネットワーク接続構成 |
| それぞれのコントローラにネットワークを接続することで、片側のコントローラに障害が発生しても、連続運用が可能になる。 |
|
|
提供:EMCジャパン株式会社
企画:アイティメディア
営業局
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2005年12月31日
|



