|
中堅・中小企業のデータ管理の問題には EMCが「大企業のためのベンダ」に留まらない理由 |
データの急増は、規模の大小を問わず、ITを使うどの企業にとってもますます無視できない重要な課題になってきている。だが中堅以下の規模の企業には特に、これが頭の痛い問題としてのしかかってきている。
どの企業でも、これまで様々なシステムを構築してきた。情報システム部が作り上げたものもあれば、業務部門単位で導入したものもある。必要に応じて必要な部署が必要なときに作ったシステムなので、利用技術の共通化が図られているわけでもないし、管理もばらばらに行われている。ストレージという観点からも、それぞれのシステムでサーバ機に内蔵のハードディスクドライブあるいは外付けのストレージシステムをばらばらに接続して使ってきた。これはしかたのないことではあるが、管理上の問題を発生させ、データ管理を困難なものにしている。
システムのなかには、最大限に活用されているものもあれば、あまり使われなくなってしまったものもある。使われなくなってしまったシステムのための記憶領域は無駄になってしまう。一方で、ファイルサーバも含め、よく活用されているシステムでは、当初用意していたストレージ容量はすぐに足りなくなり、業務に影響を与えずに、拡張をどのように円滑に行うかで苦労することになる。
これが、高機能なストレージシステムを使ったり、社内外のストレージ専門家の力を使ったりすることのできる大企業ならまだいい。
中堅・中小企業はもともと、大企業に比べればIT予算に大きな余裕があるわけでもない。社内にデータ管理やストレージに詳しい専門家がいる場合もまれで、データ管理を戦略的に考えることもできないし、実際の管理作業もままならない。問題を力任せで解決できないため、対応が後手に回り、悪循環に陥りがちだ 。
|
こうした中堅・中小企業特有の悩みを解決すべく、EMCが発売したストレージ製品が「EMC CLARiX AX4-5」だ。最小構成で約80万円と、企業向けストレージ製品としては非常に安価だ。それでもデータ量が増大するのに従って、かなり大規模なストレージシステムに育て上げることができる。この製品では、ハードディスクドライブ60台までを1つのシステムに納められるため、1TBのSATAドライブを使えば60TBという大容量のシステムも構築できる。ストレージシステム内にSASとSATAを混在させることができるため、SATAで容量をかせぎ、SASで信頼性とパフォーマンスを担保するといった使い分けもできる。
CLARiX AX4は多くの機能を備えている。より上位の製品シリーズであるCLARiX CX3のソフトウェア機能の多くがAX4でも利用できるようになっているのだ。
ポイントは、単に機能が多いというだけでなく、中堅・中小企業の担当者を楽にしてくれるような機能が提供されていることにある。最近、CLARiX AX4と同等な価格帯のストレージ製品が他社から提供され始めている。だが、製品を選択する際には、管理を本当に楽にしてくれる機能が搭載されているかどうかを見極めたい。
まず、CLARiX AX4はネットワーク・ストレージ製品だ。サーバの内蔵ハードディスクやサーバに直結の外付けストレージシステムと違い、複数のサーバのデータをまとめて格納することができる。サーバごとに管理されてきたデータを単一のネットワーク・ストレージシステムにまとめることがなぜうれしいのかといえば、ストレージ利用の無駄を減らすことができるからだ。
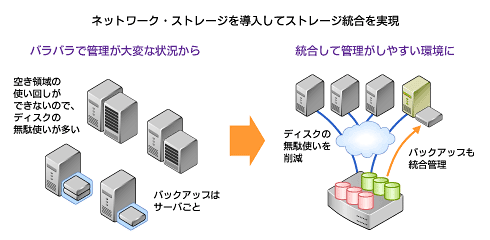 |
| 図1 ネットワーク・ストレージでストレージ機器を統合すれば、拡張や管理で有利に |
サーバごとにハードディスクや外付けストレージを用意していると、こうしたシステムは後から拡張するのが難しいため、最初に大きな余裕を見てそれぞれストレージの容量を確保しなければならない。こうした余分な容量が実際にフルに使われることはまれだ。しかし、社内にばらばらに存在しているストレージのそれぞれでストレージ容量が余っても、ほかの使い道に転用するのが困難だ。一方、ネットワーク・ストレージでストレージを統合しておけば、空き領域もまとまっているため、有効な活用方法を考えやすい。
ネットワーク・ストレージには主に2種類の技術が使われている。ファイバチャネルとiSCSIだ。CLARiX AX4ではどちらの接続方法も選択できるが、中堅・中小企業におすすめしたいのはiSCSIだ。ファイバチャネルは接続に必要な機器が比較的高価で、構成も面倒だ。しかしiSCSIならば、一般的なギガビットイーサネット機器を利用できるため安い。初期設定もファイバチャネルよりはるかに簡単だ。管理についてもイーサネットの知識を援用できるため、管理者にとって親しみやすい。
CLARiX AX4に標準搭載されている機能で、中堅・中小企業にとってもっとも便利なのは「オンラインボリューム拡張」だ。ストレージは通常、1つのシステム上に「ボリューム」と呼ばれる領域を複数設定してそれぞれサーバのOSから認識できるようにし、用途別に使い分ける。しかし、データが増加し、ボリュームの空きがなくなってしまうと、より大きなボリュームを設定し、この新たなボリュームにデータを移行しなければならない。これは通常、システムのダウンを必要とするため、管理者にとっては非常にわずらわしい、できれば避けたい状況だ。オンラインボリューム拡張では、どのボリュームにもまだ割り当てられていないハードディスク領域を使って、ストレージの稼働を止めることなく、ボリュームを広げることができる。
また、「LUNマイグレーション」という機能もある。これはストレージシステムに設定したある論理ストレージ領域のデータを、ストレージの稼働を止めずに別の論理ストレージ領域に移動できるという機能だ。
ネットワーク・ストレージに移行し、さらにこれら2つの機能をうまく使えば、必要に応じて後から簡単に領域を追加できるので、システム構築当初に無駄なストレージ容量を大量に調達しなくてもよくなる。
そしてCLARiX AX4の最大の特徴は、導入や管理に高度な専門性は必要なく、ユーザー自身が導入・設定作業を行えるという点にある。この製品の操作は非常に簡単だ。最初に電源を投入するだけでソフトウェア・ユーティリティが立ち上がり、初期設定を行うことができる。管理作業はすべてグラフィカルなインターフェイスで実行でき、面倒なコマンドライン入力をすることなく、現在の状況を把握したり、データ移行などの作業を行うことができる。
|
それにしても、主に大企業のためのストレージシステムや関連ソフトウェアを多数提供してきたEMCが、なぜ中堅・中小企業のニーズへの本格的な対応を進めているのだろうか。その裏には今後、データの急増が世界的に重要な社会的課題になるとの認識がある。
EMCの協力によりIDCが作成したレポート「膨張するデジタル宇宙」によると、2007年に世界中で生成、キャプチャ、複製されたデジタル情報は281エクサバイト(エクサバイトは10億ギガバイト)だったが、これが2011年には1800エクサバイトに増加するという。
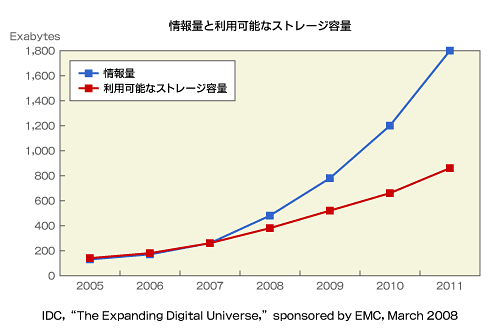 |
| 図2 情報量は、利用可能なストレージ容量を大きく超えて伸びる |
さらにIDCは、2010年までにデータの約70%が個人(消費者あるいは従業員)によって作成される一方、データの85%について、セキュリティや信頼性について何らかの組織が責任を負うことになる、と予測している。この情報爆発は大企業だけに起こるものではなく、中堅・中小企業や個人も含む社会全体で発生し、すべての分野でますますインテリジェントな解決策が求められるようになる。
この点では、EMCがそれぞれの分野に特有な問題の解決を図っているのは自然な流れだともいえる。中堅・中小企業における具体的な取り組みの姿の1つが、上に述べたCLARiX AX4であり、個人を対象とした取り組みとしては、米国で買収したバークリー・データ・システムズのオンライン・ストレージ・サービス「Mozy」や、同じく買収した「アイオメガ」の個人向けストレージ・デバイスなどがある。
EMCでは、データの急増で管理の重要性が増す状況を「デジタル宇宙」と定義し、デジタル宇宙を効率よく管理するため、情報を中心としたインフラストラクチャ、すなわち「情報インフラストラクチャ」の構築が重要だと考えている。ストレージの容量を増やすこともさることながら、各データのファイルタイプや作成年月日、内容など、さまざまな属性情報を活用して、必要なデータを必要なユーザーに、必要なときに提供できるようにしながら、ストレージの利用効率を上げられる仕組みを提供していくことが重要だ。
一方で、すべての分野に共通な課題の1つがグリーンITだ。データ量の増大は放っておけば直接消費電力やCO2の増加につながってしまう。ストレージシステムでできることは、なるべく電力を消費しないデータ格納方法を開発すること、そしてディスクドライブの利用効率を向上することだ。
EMCは2008年1月、「EMC Symmetrix DMX-4」のオプションとしてSSDドライブを提供すると発表した。データへのアクセスにおけるパフォーマンスを大幅に向上できるだけでなく、消費電力をハードディスクドライブに比べて約40%も節約できる。Symmetrixシリーズは仮想プロビジョニング機能も備えている。これは、各ボリュームへの物理ストレージ領域の割り当てを、ボリューム構成時ではなく、データ格納時にリアルタイムで行う機能だ。これで、理論的には実際に格納されているデータの量だけ物理的なストレージ容量を用意しておけば十分だということになり、ストレージの利用効率は大幅にアップする。今後EMCはこうした機能を、EMCの各種製品ラインに広げていく予定だ。
デジタル宇宙とグリーンITに加え、EMCがもう1つの使命として取り組んでいることに、「世界情報遺産保護プロジェクト」がある。これは、人類の情報遺産を保護・維持し、研究や教育の目的で重要な歴史上の資料や文化遺産を、インターネットを通じて容易に閲覧できるようにするために支援するというもの。日本では、一橋大学大学院社会学研究科のCsPR(平和と和解の研究センター)は、平和と和解に関係するさまざまな問題についての研究資料をデジタル化しようとしており、EMCはこれを援助している。
情報はデジタル化されることで、その価値が将来にわたって維持され、世界中の多くの人々が閲覧できるようになることで知を広げていけるようになる。データの量的な増大に対処するだけでなく、価値のある情報を世界が共有できるようにしていくことも、データ管理の重要な側面なのだ。
提供:EMCジャパン株式会社
企画:アイティメディア
営業局
制作:@IT 編集部
掲載内容有効期限:2008年6月27日
